Top >>Bookshop >>買物・「お金」の問題
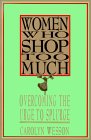 |
Women Who Shop Too Much: Overcoming the Urge to Splurge 著者:Carolyn Wesson 出版社:St Martins Pr. ISBN:0312060017 定価:$11.95 |
 |
(邦訳) 買い物しすぎる女たち 著者:キャロリン・ウェッソン 訳者:斎藤学 出版社:講談社 ISBN:4062059231 定価:1,733円 |
 |
(文庫版) 出版社:講談社+α文庫 ISBN:4062561336 定価:913円 |
思えば、本書の文庫版が発売された96年頃だったろうか。どこかの信用金庫だったと思う、女子職員による横領事件が世間を騒がせたものだった。逮捕後明るみに出た、彼女が横領した1000万だったか1億だったかのお金の使い道――毎日1万円近くを通勤にかけ、タクシー運転手の間では「マダムさん」と呼ばれていたという彼女のマンションに山積みになっていた、何十万もするブランド物のバッグや洋服のほとんどは、買ったときのまま包装紙を開けられてすらいなかったという――世間が色めきたったその“異常さ”に対し、幾人かの人々は片隅でひっそりと声を上げた。「私も同じ“病気”だ」、と。そう、「買い物依存症」という病気が発見された。 本書に書かれている買い物依存の克服法自体は、アルコールや過食や煙草なんかの数あるアディクション本の定石どおり、まず診断があって、子ども時代の影響があって、ストレスがあって、そうして自己評価を取り戻し、12のステップを踏んで、ストレスをコントロールする方法を身につけて…という感じで、私自身はとくに目新しい部分があるとは感じなかった。が、考えさせられてしまったのは、買い物依存症だった有名人として名が挙がっている女性たちのエピソードだった。 『ダイアナ、ジャッキー、イメルダ、メアリー=トッドの症例』と題されたその一章に登場する4人の女性――ダイアナ元皇太子妃、ジャクリーヌ・ケネディ=オナシス夫人、イメルダ・マルコス元大統領夫人、メアリー=トッド・リンカーン大統領夫人はいずれも、皇太子妃であり、大統領夫人や船舶王夫人であり、彼女たちの買い物依存症の法外なお金の使い方が何の摩擦も起こさなくてすむほどのスポンサーをまんまとキャッチした、今の俗な言葉で言えば「勝ち犬」女性たち、ということになるのだろう(この4人の中でイメルダ夫人だけは夫と共に地位を失い、不正資金作りの容疑で起訴されて、ついに社会との摩擦を起こしたわけだが)。 実際に使えもしないほどの量の高級商品――たとえばマルコス夫妻亡命後のマラカニアン宮殿で発見されたという、3000足の靴(10年間毎日はき替えるにしたって、その頃には流行遅れになっているだろう)、1ガロン(4リットル弱)入りのディオールのリンクル・クリーム(基礎化粧品には毎日肌につける適量というものがあるのだから、まともに使って使い終わる頃にはクリームの油脂分がひどい酸化を起こしているにきまってる)、etc.――常識ある人間の目には明らかに馬鹿馬鹿しく、病的ですらあるその浪費も、金の出所が大富豪の夫からであれば「金のかかる、贅沢な女」としてむしろ世間から羨望の目で仰ぎ見られ、エディット・ピアフや越路吹雪(彼女たちもまた結構な買い物依存であったらしい)のように自分のギャラや印税からであれば「やっぱスターは一般人とやる事が違うねぇ」で済み、一般の女性たちがクレジットカードローンに手をつけて払いきれず、自己破産に追い詰められたり、勤め先の端末を操作して会社の金を横領したり、闇金融に手を出してついに人身売買や臓器売買の餌食になったりすれば、「頭おかしいんじゃねぇか」「金にルーズな、馬鹿な女だ」「きっと男にも相手にされない、寂しい女だったんだろう」という、嘲笑まじりの非難が浴びせられる。 冒頭で挙げた信金女子職員の事件の頃にも、そんな声が聞かれたものだった。ちょうど10数年前に起こった、やはり勤め先の銀行の端末を操作して横領した金のほとんどを愛人に手渡していたという女性の事件と比較し、「好きな男に貢ぎましたっていう方がまだ可愛げがあるじゃないか、買い物中毒なんて、バカな、哀れで寂しいオールドミスだったんだろう」という心ない浅薄な揶揄もまたあちこちで囁かれた。 だが、そのあたりにこそ、買い物依存症が「女の病気」である理由が隠されているような気がしてならない。本書の『買い物しすぎる女たちを愛する男たち』という一章では、買い物依存症の女性と一緒になりやすいのは、権力志向の強い、パワーゲームの勝者になりたがるような男性である、と述べられているのだが、それこそは近代資本主義社会におけるお内裏さまとお雛さまの組み合わせではないか! 「男は外で働いて産業の発展に努め、女は家に引っこんで、夫の安らぎの場である家庭を守ることと、次世代の優秀な労働力である子を産み育てることに専念する」というのが近代家族のモデルであるといわれるが、そのような価値観の中では、もっとも成功した勝者とは、実業家なり政治家なり王族や貴族なり、ともかく金と権力を持っている男と、その男のステータスシンボルとなりうるような美しく贅沢な妻のことだ。働く女ではステータスシンボルになりにくい。自分では働かないで金を喰う女であることによって、排気量の多いメルセデスやフェラーリのようにそれだけ維持費が高くつき、夫のステータスシンボルとなる。料理も掃除も育児も、お金によってお抱えのシェフやメイドや乳母にアウトソーシングできる、ということもまた財力の象徴だ。かくて、“美しく贅沢な妻”の仕事は、浪費することだけとなる。 そのように、私たちは小さい頃から“女の子の成功物語”を刷り込まれてきている。女の成功とは「愛されること」だ、「愛される」とはすなわち「大事に扱われる」ことだ、「大事に扱われる」とはすなわち「金をかけてもらえる」ことだ、食べさせてもらえて、服や宝石や毛皮を買ってもらえることだ、と。買い物依存なんて、男に金をかけてもらえない寂しい女の欲求不満なんだろうよ、という揶揄は、半分だけは正しいかもしれない。確かに、買い物依存で生活を破綻させてしまった女性たちの多くは、孤独感から浪費に走った、と言う。だが、本書の症例にある“成功者”である有名女性たちもまた、結婚した時点ですでに夫に愛人がいたり、妻である自分をステータスシンボル=高級車やヨットと同じような“モノ”としてしか見ていない夫との冷え切った結婚生活の果てに、病的な浪費へと走っている。現実逃避、そうして、シンデレラ物語を生きるお姫様であるはずの自分、「金をかけてもらえる女」の病的なカリカチュアを演じてみせることでの、無力な意趣返し。桁外れの財力をもった権力中毒の男はここでは、またとないイネイブラーだ。「贅沢な女」を一人満足に抱えておけないというのは、一個のステータスシンボルを満足に抱えておける力が無いと同じことで、権力者である自分の沽券にかかわることだ。だから、ギリシアの船舶王アリストテレス・オナシスは、妻ジャクリーヌから当てつけのように回されてくる山のような請求書に無言で金を払い続けた。 それでもいいもん、と相変わらずシンデレラストーリーに憧れる女の子たちは無邪気に言うかもしれない。だが、「贅沢な女」も年月が経てばただの「欲ボケ婆あ」として周囲から疎まれることだろう。もう一度若く美しい容貌を手に入れて「ゴージャスな女」をやろうったって、今度は「欲ボケ婆あ」プラス「美容整形サイボーグ」という嘲笑がくっつくのがオチかもしれない。「金をかけてもらえる女」が手放しで賞賛・羨望されるのは、彼女自身の肉体に商品価値がある間だけのことだ。誰もが羨むステータスシンボル=商品として最高の値をつけられるために、金をかけて飾り立てられているのだから。この資本主義の論理の中での“女の子の成功物語”とは、じつはそういうからくりになっている。歳をとってオバさんになって、金だけは湯水のように浪費できても若い愛人を作っている夫にないがしろにされているシンデレラの訴えに耳を貸す世間などない。シンデレラの物語は、お城での王子様との盛大な結婚式という、彼女が商品として最高の値をつけられた瞬間で終わっているのだ。“商品”、それもすでに買われて手垢のついた“商品”が心の痛みを訴えたって、この資本主義社会は「ハァ?」と怪訝な顔をするだけだ。 近代の資本主義社会において、「美人である」ということは「金をかけてもらえる」ということ、つまり金をかけてくれる金持ちの親なり男なりパトロンなりがいるということだった。そして近代フェミニズムの出発点とはじつは、「あたしは確かに貧乏かもしれない、でもブスじゃないもん!」ということなのだ――作家の橋本治氏は『貧乏は正しい!』の中でそう言っている。4人の買い物依存症者たちの中で、ダイアナはボランティア活動、ジャクリーヌは出版編集者という仕事を得たことで、病的浪費から立ち直っていったという。仕事が買い物依存に対する万能薬ではないし(買い物依存症の働く女性もいるのだから)、「やっぱ金じゃなくて愛情のある男を見つけることだよ」と言われたって、それではただ単に買い物依存がしがみつきの人間関係依存にすり替わってしまうだけの可能性は大いにある。この世の中は何だかんだ言いつつ、商品を買え買えと、買い物依存を奨励している。たぶん、その罠にハマらないで済むための、あるいは罠から脱け出せるためのカギは、女の価値(に限らずこの社会での人間の価値)は「愛されること」=「金をかけてもらえること」という幻想を一歩引いてつき放した目で見ることができるかどうか、そして、たとえ孤独でも、内側から自分を温める何かをもっているかどうか。そこにかかっているのではないか。買い物しすぎる“女たち”というタイトルを眺めながら、そんなことを思った。 (2005/01/01 蔦吉) |
|
